🐚 三重県の史跡
今日も来てくれてありがとう!よければ一押しポチっと応援してってね〜。伊賀上野城として残されている現存エリアには、伊賀流忍者博物館(からくり忍者屋敷や忍者実演ショーなども楽しめる)や芭蕉翁祈念館(芭蕉の旅姿を模した国指定重要文化財である俳聖殿など)があるためか、訪れている人は多く、そしてどこかウキウキしたエネルギッシュな雰囲気が満ちている。時間の関係もあり伊賀上野城のみに狙いを定めた私は、苔むした古い石垣に心奪われながら整備された石畳をのぼっていく。

開けた広場に足を踏み入れ少し歩いたところで、こんな親切なお城みたことあったかな?ってアッとした。城代役所跡と記された場所では、居間周辺、長屋群、広間、次書院などと各場所ごとに看板や地面直付けプレートらが取り付けてあり、まるで内覧をしている感覚を味わえる。
古い石垣が残る台所門跡にも、柴小屋、米蔵、塩噌蔵とか各場所にプレートがつけられていて当時の様子が脳内で容易に展開されていく。裏門なんてプレートもあった。

伊賀上野城はとにかく石垣と、石でできた階段とか石の存在に息をのむ。城内に入るとそこはもう博物館そのもの。軍扇、羽織、馬籠、刀、鎧兜など当時の物が所狭しと展示してあり、生々しい。忍者装束に身を包んだ等身大の複数の忍者人形が天井近くにはり付いていたり、壁をはっていたりなどの演出もあり、遊び心もあって楽しい。

2階にも沢山の展示物。錦絵、書や絵の掛軸、巻物、陶器などの芸術作品。1階の戦国時代が終わり平和な文化の時代になったんだな~とホッとしたのもつかの間、いきなり登場する『敵方の首級を包んだ母衣絹』。褒章Getの為の証拠品としての血だらけの首を包んで持ち帰るための専用布があったとは。それを忍ばせ戦場に赴いていたということか。陣鍋などもあり冷え切った携行食だけでなく戦場でも状況によって温かいものも食べれたんだなって少しほっとした。
「大阪夏の陣の足軽などの行装についての覚書」なんかを見た時は、そんな細かい規定があったのには驚いた。「贈り物への礼状」などの巻物やらも広げた状態でいろいろ展示があった。藤堂高虎仕様の膳部や蒔絵手箱や家具調度品なども展示されていて当時、城内に高虎が居る時の様子が目に浮かぶようだった。

3階の天井絵巻は思わずため息が出るような立派さ。一枚1メートル四方の大きな紙、横山大観や尾崎行雄などなどの著名な画家、書家、政治家などから寄贈された46枚の書画が天井をいろどる。上を見ているだけで情報量が豪華で実に見事。1611年ころの大暴風で天守閣が倒壊し、川崎克氏が昭和10年(1935年)に復興した天守閣竣成を祝い贈られたものだという。
さて、外に出ると、「キケン」と赤字で目立つように地面にたてられた看板がひときわ目を引く。看板を無視して端まで行くと‥‥そこはもう柵も何もない石垣の崖!これは圧巻!

見た瞬間に思った。これ、のぼるの無理じゃん!って。藤堂高虎が築いた高さ約30メートルのこの石垣は、大阪城の石垣と並んで日本で1、2位の高さを誇る。お城最上階と同様に伊賀市の城下町や周辺の景色を一望することができる。
お土産処では、「藤堂家家訓」とか「天井絵巻の写真付き説明本」とかも販売されててセコイ私が思わず買いそうになってしまったほど魅力的だった。
【伊賀上野城 歴史編】
伊賀上野城があった場所は、古くから伊賀国の中心地の1つだった。山深い伊賀の地は古くから守護大名などの支配が及びにくく、地元の土豪(有力な在地領主)たちが連合して強力な自治組織「伊賀惣国一揆」を形成していた。
彼らの評定所が、後に上野城が築かれる地にあったと伝わる。 しかし、独立性の高い伊賀国は、1581年の織田信雄(信長次男)の天正伊賀の乱で平定されてしまい、伊賀衆は滅亡・解体されてしまう。
1585年に筒井定次(豊臣秀吉の家臣)が、伊賀の再支配と大阪城の東の備えとして、現在の伊賀上野城の地に上野城(のちに筒井古城と呼ばれる) を築いた。
江戸時代に入ると1608年に藤堂高虎が、伊賀・伊勢(津藩)の領主となり、徳川家康の命により豊臣秀頼が籠る大阪城に対抗するため上野城を基礎に、大規模に改修・拡張した。

圧倒されるあの石垣も、築城の名手・藤堂高虎により築かれたもの。高虎は南西の要所に幅約30メートルの深堀を構え、南・西両面に大阪城よりも見事!と今に伝わるほどの大石垣を新しく築いた。 さらに、南北の両隅には櫓台をつくり、当時(筒井定次時代)の本丸と合わせて新本丸とし、3倍の大きさに拡張改修した。
さらに、南に面しては、2つの出入り口を開き、東は古き空堀とした。
本丸東側には、筒井定次が最初に築いたお城(筒井古城)の石垣の一部が残っている。

1611年(慶長16年 )ごろの暴風で天守閣が倒壊したと伝わる。 1614年1615年の大坂の陣で豊臣家が滅亡したため、軍事的必要性がなくなり天守閣は再建されることがなく幕末を迎えた。明治時代の廃城令でお城は取り壊され、城跡と高石垣だけが残った。
1935(昭和10)年に、地元出身の衆議院議員・川崎克氏が私財を投じて木造で天守閣を復興。内部は歴史資料館・美術館となっている。藤堂高虎が秀吉から拝領した唐冠形兜などが展示されている。
今でいうプロの工作員集団・伊賀忍者の里。織田政権により一度は壊滅したものの、江戸時代には伊賀者・甲賀者として幕府に仕え、隠密や御庭番として活動を続けた。彼らの里は哀愁とそれでも存続し続ける物凄い底力をひしひしと感じた。
行けば必ず感動する一度は訪れたいお城の一つです。遊び処もたくさんあり一日たっぷり楽しめます。
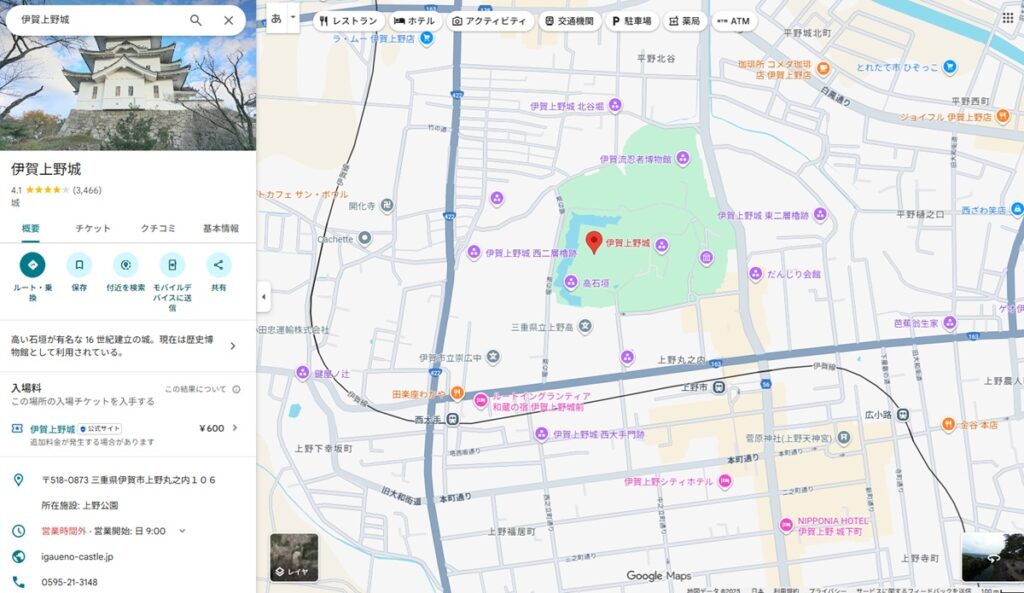
伊賀上野城の写真一覧














2020/03






コメントを残す